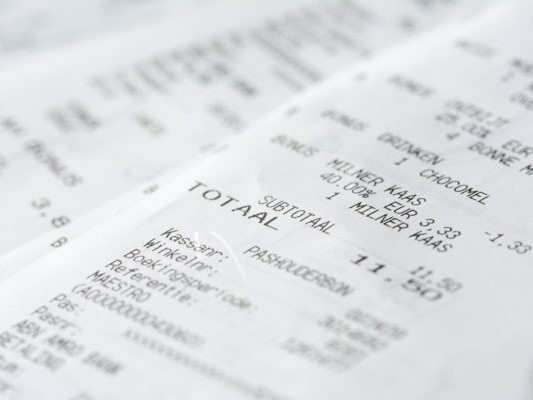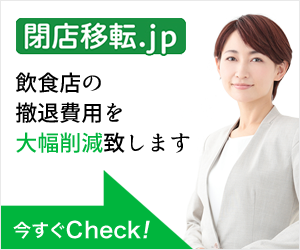繁盛する飲食店には売上がアップする接客方法と魔法の言葉が存在した
Contents
サービス料の起源
そもそもサービスの概念は明治時代、西洋文化と共に持ち込まれたものです。ただ、もともとサービスに対する対価ではなく、西洋の飲食店では当たり前のチップに替わるものだったと言います。 ここで疑問が出てきます。もしサービス料がチップに替わるものであったならばどの飲食店を訪ねてもサービス料が請求されるはずです。 皆さんご存知の様にそのようなことはなく、請求されるのは高級店やホテル、またお酒を提供するお店など客単価が高いお店に限られています。なぜなのでしょうか。 そのカギが戦前の爵位にあるとされています。男爵、子爵、伯爵など高貴な家柄、または国家に多大なる功労があった人物に与えられた称号ですが、早くから西洋の見聞をし、その文化をいち早く取り入れた方々でした。 当時外で食事をするという文化は限られた特権階級である彼ら以外にあまりなく一般大衆が利用することはなかったようです、そんな彼らがお店を利用した際にチップを出したと言います。故に彼らが利用した高級店のみにサービス料が残ったようです。サービス料とチップの違い
サービス料がチップから派生しているなら似た取り扱いとなるはずですが、大きな違いがあるようです。金 額
- サービス料: 飲食代金 10% ~ 20% (一律徴収)
- チップ : 飲食代金 10% ~ 15% (任意)
支払先
- サービス料: お店に代金と共に支払い
- チップ : 店で働く個人に支払われる
税扱い
- サービス料: 消費税対象、売上に計上
- チップ : 消費税対象外、個人収入
小規模飲食店の新人教育は5つのポイントで早期戦力化と定着化!決め手はアレです
サービス料を請求するには
何の説明もなくサービス料を請求されたらどうでしょうか。後出しジャンケンのようで腹を立てるお客さんが続出することでしょう。そうなればお店の評判は悪くなり本末転倒の事態に陥ります。 サービス料を頂こうと考えるなら注文時にお客様がサービス料の事を理解している必要があります。 メニューに「当店ではサービス料〇〇%を申し受けます」などの表記をするか、ホテルで見かけるようなお店の入り口に「当店ではお支払いの際にサービス料〇〇%を申し受けます」の表記を目につく場所に掲げる必要があります。 つまり、お店で食べる方もちゃんとサービス料の事を理解してオーダーした訳ですから当然支払う義務が生じるという契約関係が成立する必要があります。 これを冒頭の居酒屋の様に、お金を支払う段になってサービス料を請求するのでトラブルになってしまうのです。逆に言えば、契約関係が成立していないので支払う義務はなのです。サービス料に替わるもの
なかなかサービス料は他店とのバランスもあり請求しづらいとお考えの経営者の方多いと思います。飲食の世界では様々なチャージ料に匹敵するものがあります。 お通しや突き出しもその一つです。だいたい頼んでもいないのに提供され、支払時にはおおむね300円~500円程度の金額がついています。実はチップに慣れた欧米人でもこのことに疑問を感じる人が少なくないと言います。 特にドイツからの観光客は細かくレシートをチェックし、オーダーしていないものにお金を払わないそうです。 このところ大手の居酒屋チェーンではお通しを断ることが出来るところが増え来ましたが、コロナによる入国規制解禁後、海外からの観光客が増える中で何らかの対策が必要だと思います。 同様にお酒を提供するお店で見られるチャームやチャージと呼ばれるものも同じ様なものです。チャームは簡単なおつまみ、チャージは言うなれば席料です。お店の業態、形態は違えども形を変えたサービス料は存在するのです。まとめ
サービス料がチップから派生したものに対しチャームやチャージは別の理由から派生して来たと聞いたことがあります。 今では当たり前となっているボトルキープサービスですが、戦後ウイスキーが贅沢品だった時代に考え出されたリピーター造りの方法だったのです。 ところが思わぬ落とし穴があったのです。ボトルキープした人が来店され自分のウイスキーだけを飲んでいたのでは、売上に貢献しないし、他のお客様が入店出来ない事態にもなるので、考え出されたのがチャームとチャージだというのです。 なるほどという話ですが、こちらもサービス料同様、時代にそぐわなくなった遺物のような気がします。いずれにせよ形をかえた課金ではなく、提供する料理やお酒で勝負して頂いた方がお客様としては納得してお金が払えるのではないでしょうか。繁盛している飲食店が 「お通し」にかける情熱と秘訣を大公開