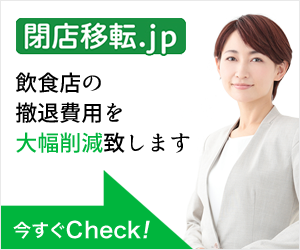Contents
成功している飲食店の共通点 – まとめ –
- 厨房がメニュー、動線に合わせた造りになっている
- 1席たりとも無駄にしない
- 看板メニューが必ずある
- 常にメニュー構成を工夫している
飲食店は厨房の作りが利益に直結!
まず最初に考えて頂きたいのが厨房の設計です。スケルトンであればいちから自由に設計できる楽しみがありますがその分コストがかかります。 これに対し居抜き物件は、既に一通りの設備が整っているためさほどコストをかけずに飲食店を開くことが出来ますがその反面使いづらさは否めません。 実はどちらも共通のミスを犯す可能性が非常に高く、あるポイントをおさえてスタートしないと利益が出ないお店になってしまいます。 そのポイントとは「厨房機器のレイアウト」です。まず、居抜き、スケルトンともに同じ間違いを犯すと言った部分を解説します。 飲食店不動産物件に関し、特にスケルトンの場合、ガス、水道など「バルブ止め」と言って床や壁からパイプやメーターが出ているところまでの仕上りで引き渡されます。最近の店舗物件だと換気扇や有圧扇などが既につけられているものもあります。 この状態から厨房の設計を考えると出来るだけ無駄のないようにしようと、建物側の意図に沿った水道、排水、それにダクトの下にガス配管を考えます。図面上は非常におさまりが良いのでその時点で問題点に気づく人はまずいません。 ここで立ち止まって考えてみて下さい。本来厨房のレイアウトとはどのような料理を作るのかによって決まるべきです。決して建物の設備に合わせるものではありません。 実はこのことが後に居抜き物件として引き継がれていく際にも同じ過ちを引き継ぐこととなるのです。飲食店舗 利益が出る厨房レイアウトはこれだ!~作り方のノウハウをプロが徹底解説~
飲食店厨房のレイアウトの問題は一体どこに
まず第一に、動線などの作業効率があげられます。 厨房の中を1日何歩歩くのか考える必要があります。仕込み材料を取りに行く、材料を取りに行く、切り分ける、焼く、煮る、盛り付ける、洗うと言った一連の作業が最小歩数で出来るよう考えるべきです。 良い例では、コの字型カウンターの立ち飲み居酒屋があげられます。1日100人以上を相手する繁盛店のご主人はこういっています。「全ての料理を2歩以内で完成できないとお客様の数に対応できない」と。 ここから二つの事が見えてきます。歩数が多いということは料理に時間がかかることを意味します。料理に時間がかからないようなレイアウトであれば、3人で切り盛りしていた厨房は2人で済むことになります。 そうなれば人件費を切り詰めることが可能となります。当然、ランチ時や夕方一度にお客様が来店される時間でも料理を待たせることなく給仕することが可能となります。 一般的言われている料理を待たせる限界時間ですが、着席スタイルで15分、夜のお酒を出すスタイルでも20分がリミットです。これ以上待たせることになるとお客様は以後来店頂けなくなります。 次に問題になるのがデシャップと下膳そして皿洗いシンクとの関係です。 出来上がった料理を一時的に置く場所をデシャップと言いますが、この場所と下膳をする場所が同じ場所というお店を見かけます。汚れた器の隣に出来立ての料理。お客様はどう思うでしょうか。 また、繁忙時となるとお皿を洗う暇が無くなり下膳が場所をとって行きます。その時直ぐに下げた器をシンクに入れられれば問題ないのですが、デシャップのスペースがなくなり結果カウンターの1席を潰してしまっているような飲食店をよくお見受けします。 この場合、見た目や作業性以上に1席を潰すことでランチだけでも、客単価900円、1日に2回転するようなお店であれば、月に4万5,000円、年間54万円の損失となります。 特に居抜きで飲食店を手に入れられた方は諦めずにレイアウト変更を考えるべきです。すぐに元は取れます。飲食店の客単価が上がるメニュー作り=レイアウト・価格設定・ネーミング
飲食店が繁盛するにはメニューバランスを考える
お店にお邪魔してお薦め料理を伺った時の事です。「ウチは全てがオススメ料理。どれを食べても美味いよ」と言われたことがあります。 お気持ちはよくわかります。結構自分の得意料理や今まで受けの良かった料理ばかりを取り揃えて飲食店を始める方も多くお見受けします。ただこの場合、いくらそれぞれの原価を切り詰めても利益の出ない落とし穴があるのです。 まず、全ての料理が一般的に言われる飲食店の原価率30%だったとしましょう。この時小さな飲食店で提供されるメニュー数と言われるのが30~40品です。これら全て満遍なく売れれば何の問題もありません。 ところが現実はそうではありません。実際には3分の1程度のメニューで7割から8割を売り上げているのが一般的です。逆に言えば3分の2は売り上げの1割から2割しか貢献していないことになります。 となればどうなるでしょうか、当然廃棄しなければならない食材が増えることになります。もしすべての料理が同じような価格帯だとすると売れない料理が多い分売れている料理の利益を食いつぶす結果になります。これではお金は残りません。 そこで繁盛する飲食店が取っている戦略は、「原価の高い看板商品」で集客して原価率の低い料理も併せてオーダー頂きお出しした料理すべての平均原価率が30%になるようなメニュー構成にしています。 看板料理用に仕入れた食材は無駄になることはありませんし、逆に注文の少ない食材が仮に廃棄することになっても原価がかかっていな分利益は残ります。~まとめ~
最近の傾向として料理のバラエティー化が進んでいるように思います。一点豪華食材や高級部位や希少品種というものよりも、水揚げした場所の異なる生ガキなどを三種類盛り合わせたものやマグロでも部位の異なる赤みの盛り合わせるなど単品では高くなるところを少しづつでもよいものを食べられるようお得感を演出しています。 洋食で言えばコース料理がそれにあたります。アラカルトですべてをお客様に選ばせるより店側の推薦組み合わせで原価率や一皿の盛り付け量を調整して提供すればお客様もお店もハッピーとなる仕掛けです。 飲食店の命はコンテンツである「料理=味」です。しかしご自身で経営をするということになれば構成力や宣伝力といたものが必用になります。なによりお店を訪れるお客様の最大の関心事であるコストパフォーマンの高さをどのように演出できるか重要なポイントです。 繰り返しになりますが、飲食店を始められる前には厨房のレイアウトの工夫、メニュー構成など十分に検討なさってください。飲食店儲かりの秘訣は「ターゲット」・「立地」・「価格」と競合調査を実施せよ!