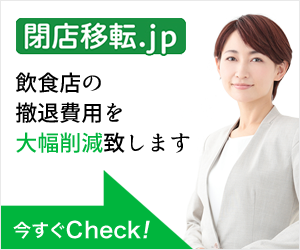Contents
飲食店のプロ開発担当者が見ているポイント
店舗開発を手掛けるプロの方々は、まず人の流れに注目します。通りごとの評価や同じ通りでもどこまでが開業の可能性があるのか、つまり左右どちらのサイドならいいのか、電柱1本の距離までまでこだわって調べます。方法はこうです。- ランチの時間(11:30~14:30)
- 夜の早い時間(17時~20時)
- 夜の遅い時間(10時~終電)
- どの層に利用されるのか
- 価格帯はどこに設定するのか
- 時間帯は遅くまで可能か否か
- 競合となる価格帯の飲食店に出向き繁盛しているのかどうか
- 差別化をするには価格なのかボリュームなのか
アフターコロナで飲食店が繁盛する5つのアイディアと3つの宣伝方法
個人で間単にできる飲食店のマーケティング
店舗オーナーが開業前に出来るマーケティングですが、簡単な方法があります。早朝のゴミ収集の時間にゴミのチェックをする方法などです。 何に着目するのかといえば、飲食店のゴミの量や空き瓶の種類や数です。- どの曜日が忙しいのか(この地域では)
- どこの店が流行っているのか(どの競合店が流行っていて)
- どんな酒が良く出ているのか(何が好まれているのか)
- どのくらいごみを排出しているか(どのぐらい売れているか)
飲食業界のトレンドをつかみ改善のヒントに
さて、このゴミチェックは一度やれば終わりと言うものではなく継続することで威力を発揮します。曜日や季節、天気などと併せて記録を取り続けることで、トレンドが見えてきます。 つまり食材や料理の流行と廃れなどです。ここ数年は肉系の料理が人気でしたが、そこに鯖が加わってきています。以前は、ブリなどを使った鍋が流行ったこともありましたが今では下火となっています。こういったトレンドを掴むことができますので、競合店に先んじてニーズの移り変わりを知ることができるようになります。 定番のメニューだけで太刀打ちできないと感じた時や流行のメニューに衰えを感じた時など、どう手を打って良いのか迷うものです。でも、このような地道なマーケティングを続けていれば無用の心配と言えます。料理以外の飲食店利用客ニーズを把握する
そもそも客のニーズを把握しないで提供する商品やサービスは、押し売りでしかありません。 「いかがですか?」「どうですか?」「是非使ってください!」と言っていても客が求めてなければ、まったく意味を成さないのです。客が来ないと悩む前に、客が求めているものを提供できているのか?先に考える必要があると思います。 その意味で飲食店から出るゴミと言うのは、ニーズの消費された結果ととらえることができます。 ただ、ニーズのマーケティングで注目したいのがメニュー以外の部分です。 例えば、なんのとりえもない飲食店が物凄く繁盛しているのはなぜだろうと不思議に思うことがあります。その場合、人目を気にしないで利用できる個室があることが理由だったり、禁煙のお店が増える中で全席喫煙OKだったり、深夜までやっている唯一のお店だったりと本来の目的と違た利用のされ方がお店の売上を左右することがあります。 これはその飲食店の立地に起因することが多く、周辺環境がオフィス街なのか、街工場が混在するエリアなのか、住宅地なのか、お店を利用するお客様の平均所得や生活習慣にも注目することで見えてくるものです。~まとめ~
結論として、飲食店のマーケティングは、- 街のトレンドをもとにメニューをアレンジする
- 飲食店が利用される食事以外の目的を掴む
飲食店を悩ませる宣伝・稼働率・距離の問題を新しい発想で解決する